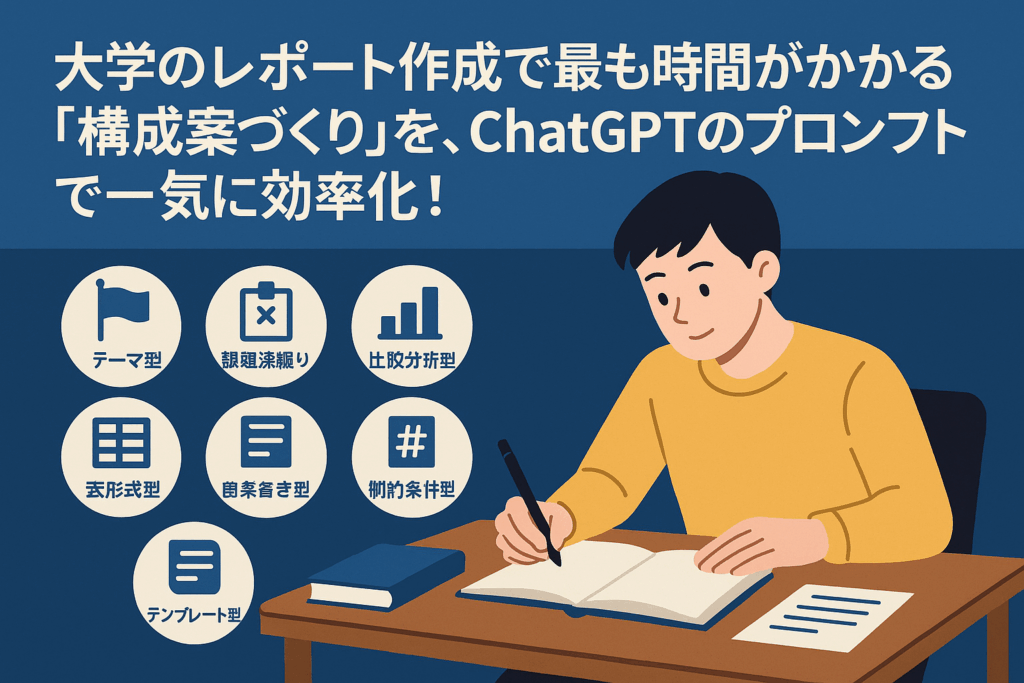
1. レポート構成自動化のメリットとプロンプト設計のポイント
レポート構成自動化のメリット
1‑1. 作業時間の大幅短縮
AIプロンプトで見出し案を即生成することで、従来数時間かかっていた構成作成が数秒で完了します。
1‑2. 論理的な見出し設計が誰でも可能に
背景・課題・目的など学術論文の基本要素をAIが自動で整理し、漏れなく論理的な骨組みを提案します。
1‑3. 初心者でも質の高い骨組みを作れる理由
テンプレート型や制約条件型など多彩なプロンプトパターンを使い分けることで、AIが最適な構成をガイドしてくれます。
良いプロンプト設計の3つのポイント
2‑1. テーマと目的を明確に
「何について」「何を達成したいのか」を具体的に示すことで、AIが的確な見出しを生成しやすくなります。
2‑2. 出力形式(H2・H3数など)の指定
「H2は○本、H3は各H2に△つ」のように、階層構造を明示すると、期待通りのアウトラインが得られます。
2‑3. 具体的キーワードの網羅
キーワードリストを併記しておくと、AIが重要テーマを漏れなく盛り込んだ構成案を提案します。
大学のレポート作成で最も時間がかかる「構成案づくり」を、ChatGPTのプロンプトで一気に効率化!この7つのパターンを覚えれば、どんなテーマでも数秒でアウトラインが完成します。
2. 一般テーマ型:「背景→課題→目的→見出し提案」
最もベーシックな構成パターン。背景・課題・目的を整理し、H2見出しを提案させます。
そのままコピーできるプロンプト文:
「以下のテーマに対し、『背景・課題・目的』を各100字でまとめ、H2見出しを4つ提案してください:
『大学生のオンライン授業における集中力低下の原因と対策』」出力例:
背景(100字)
オンライン授業の普及に伴い、対面授業と比べて学生の集中力低下が問題視されている。課題(100字)
教材への没入感不足や環境整備の不十分さが、学習効率の低下を引き起こす要因となっている。目的(100字)
原因を分析し、オンライン授業でも高い集中力を保つための具体策を提案する。提案H2見出し
1. 集中力低下の主な要因分析
2. オンライン学習環境の最適化方法
3. テクノロジー活用による集中力向上策
4. 実践事例と評価指標
3. 課題深掘り型:「問題提起→要因分析→解決策→まとめ」
「問題提起→要因分析→解決策→まとめ」の4ステップでレポート構成を自動生成します。
そのままコピーできるプロンプト文:
「テーマ『キャンパス内ゴミ問題』について、
1. 問題提起
2. 要因分析
3. 解決策提案
4. まとめ
の順に、それぞれ見出し案と100字要約を作成してください。」出力例:
1. 問題提起
キャンパス内に散乱するゴミが環境美化と学習環境に悪影響を与えている。2. 要因分析
学生のマナー意識不足、設備配置の不便さ、啓発活動の不足が主因である。3. 解決策提案
ごみ箱配置の最適化、キャンペーン実施、分別ルールの徹底などを提案。4. まとめ
総合的取り組みにより、キャンパス美化と学生意識向上を図る。
4. 比較分析型:「A vs B → メリット・デメリット → 総合評価」
2つの対象を比較するレポート向け構成。見出しで対比を鮮明にします。
そのままコピーできるプロンプト文:
「『紙の図書館利用』と『電子図書館利用』を比較し、
1. 比較ポイント見出し(3つ)
2. それぞれのメリット・デメリット見出し
3. 総合評価見出し
を提案してください。」出力例:
比較ポイント
1. アクセス性 2. コスト 3. 資料検索効率紙の図書館利用のメリット・デメリット
メリット:実物資料の深い理解、静かな環境
デメリット:開館時間制限、移動時間電子図書館利用のメリット・デメリット
メリット:24時間アクセス、検索機能強力
デメリット:目の疲れ、著作権制限総合評価
目的次第で使い分けるハイブリッド活用が最適。
5. 表形式型:「章立て→表見出し→項目列挙」
表を使った比較を含むレポートに便利。表の見出しと列項目を自動生成します。
そのままコピーできるプロンプト文:
「テーマ『大学生の時間管理術』について、
– 章立て(H2見出し3つ)
– 各章で使う表見出し(列名3つ)
を提案してください。」出力例:
H2見出し
1. 日々のスケジュール管理 2. 長期計画策定 3. 効率化ツール比較表見出し(列名)
・方法名 ・所要時間 ・メリット/デメリット
6. 箇条書き要約型:「H2見出し→H3で箇条書きポイント」
H2で大項目を決め、H3以下に3~5項目の箇条書きポイントを作成。
そのままコピーできるプロンプト文:
「テーマ『大学の就職支援サービス活用法』について、
– H2見出し3つ
– 各H2下にH3で箇条書きポイント4つ
を提案してください。」出力例:
H2-1: サービス概要
– キャリアセンター予約方法
– オンライン相談利用法
– イベント参加メリット
– 情報収集手段H2-2: 効果的活用術
– 事前準備のコツ
– フィードバック活用法
– ネットワーキングのポイント
– 継続的フォローアップH2-3: 成果を上げるために
– 目標設定手法
– 定期レビュー方法
– ピアサポート活用
– 成果の見える化
7. テンプレート適用型:「論文フォーマット→セクション割当」
学術論文ライクな構成を望むときに。「序論→方法→結果→考察」の章立てを自動生成します。
そのままコピーできるプロンプト文:
「テーマ『キャンパスの再生可能エネルギー導入効果』を、
– 序論
– 研究方法
– 結果
– 考察
– 結論
の順で見出し案と50字要約を作成してください。」出力例:
序論: 大学キャンパスのエネルギー消費と環境負荷を概観。
研究方法: シミュレーションモデルによる導入シナリオ比較。
結果: 太陽光+蓄電池併用でCO₂排出率が30%削減。
考察: 導入コストと運用メリットのバランス分析。
結論: 段階的導入が最適と判断。
8. 制約条件型:「文字数・視点指定→構成提案」
特定条件(文字数、執筆視点、対象読者)を加えて、より詳細な構成案を得るパターン。
そのままコピーできるプロンプト文:
「テーマ『オンライン授業のメリット』を、
– 500字以内
– 高校生向け視点
– 箇条書き構成
でH2見出し3つと各50字要約を提案してください。」出力例:
H2-1: 学習の柔軟性
オンライン授業は時間・場所を問わず学習可能で、自分のペースで進められる。H2-2: 資源節約
通学時間や紙資料が不要となり、コストと環境負荷を削減できる。H2-3: 技術活用スキル向上
オンラインツール操作を通じて、ITリテラシーが自然に身につく。
9. まとめ:まずはこの7パターンから試そう
- どのテーマにも使える「背景→課題→目的」型
- 比較・分析、表形式、論文スタイルなどバリエーション豊富
- 条件指定でさらにカスタマイズ可能
まずは自分のテーマで3パターンを試し、最適な構成法を見つけましょう!

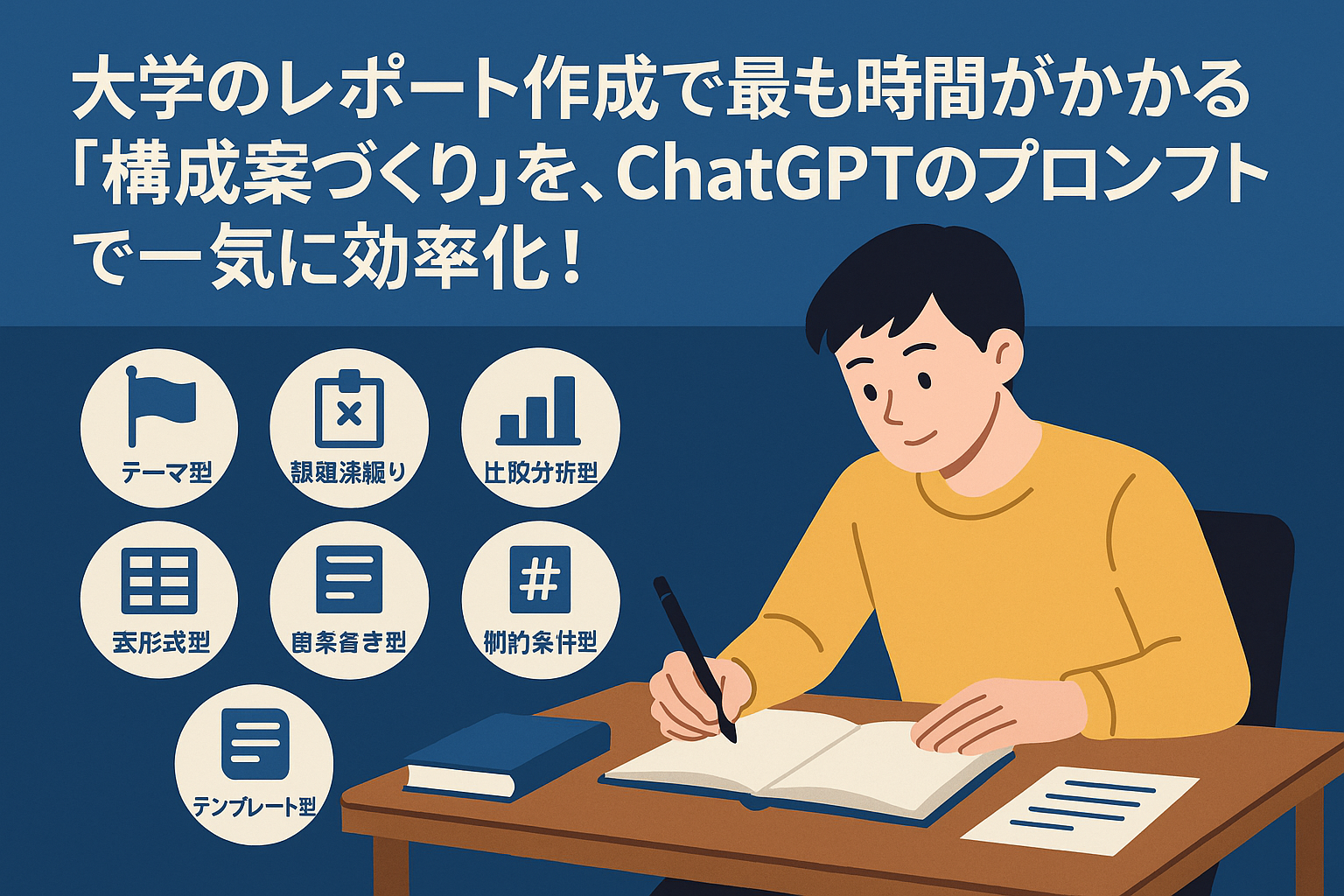
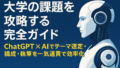
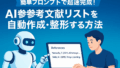
コメント